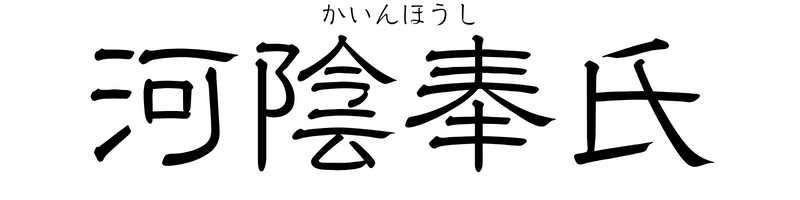世不明。飢民救済請願を上書。
奉議(ほうぎ)は、奉説と同じく『河陰奉氏大同譜全』には掲載されていない。こちらも『河陰奉氏世蹟録』によると、高麗史という高麗王朝の史書に登場している人物である。
忠穆王(ちゅうもくおう)4年(1348年)2月、征東行省(せいとうこうしょう)都事(とじ)の岳友章(がくゆうしょう)と、配下の員外郎の石抹完澤(せきまつかんたく)そして奉議は、王に以下の上書を提出した。
「深く憂慮すべきは、民衆が飢え死にしている現状が長引く不作によるものであるということです。特に西海道(現在の黄海道)、楊廣道(現在の京畿道)、開京(高麗首都)などでは、昨年の干ばつ、洪水、霜害により作物が枯れ、多くの人々が命を落としています。これは誠に悲しく、憐れむべき事態です。
高麗には官吏の選抜に関する法規がすでに存在します。そこで、元朝の納粟補官(にゅうぞくほかん)の例に倣い、飢饉に苦しむ民衆を救済するため、穀物を献納することで官職を得る制度を設けるべきです。これは、先王たちが民を救済しようとした精神に沿うものであります。
穀物を献納して官職を得る場合、官職に就いたことがない者は、従九品であれば米5石、正九品であれば10石、以下、従八品15石、正八品20石、従七品25石、正七品30石を上限とし、これ以上の献納は認めないこととします。また、以前官職にあった者が米10石を献納する場合は、官位を一つ昇進させますが四品までとし、三品以上の官職には適用しないものとします。」
征東行省:日本侵攻のための軍事機関。遠征失敗(元寇)後は高麗を統治する軍政機関となった。
都事:征東行省の官職。
員外郎:尚書六部(吏部、戸部、礼部、兵部、刑部、工部)に属する六品官で定員外。
忠穆王:第29代高麗王(在位1344年〜1348年)。
いわゆる納粟補官(のうぞくほかん)とは、穀物を納付した人の身分と納付量に応じて官職を与える制度であり、これを利用して国家の倉廩(そうりん)を潤し、困窮した民に施そうというものである。
奉議らは高麗の各地域で干ばつ、洪水、霜害による凶作が発生し、多くの民が深刻な飢餓に苦しんでいる現状を憂慮して、民を救済するために、穀物を献納することで官職を得ることを王に提案した。
飢饉対策が一番の目的であろうが、官職を得る機会を増やすことによって官僚組織の活性化や献納された穀物を政府の財源として活用することも狙いとしてあったことであろう。
結果としてどうなったか不明であるが、上書をしてまで民を恤救(じゅっきゅう)しようとする志はとても立派で、大層な人物である。しかしこれだけの人物なのにどうした訳か、『河陰奉氏大同譜全』には記載されていない。謎である。